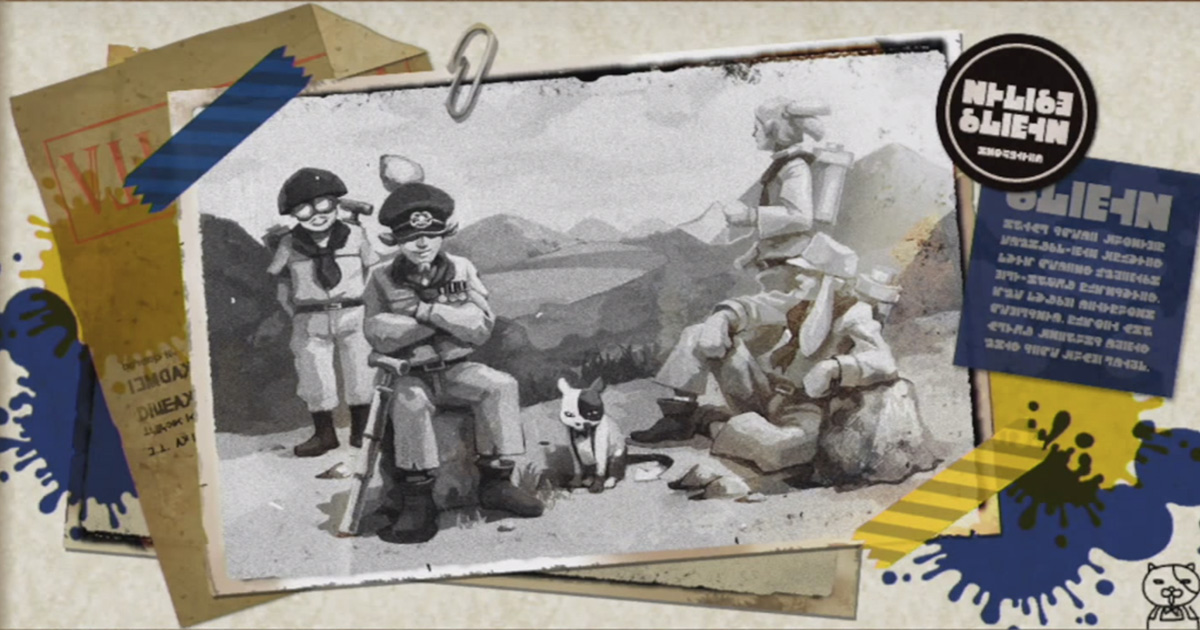歴代ゲーム機の開発コードネームがどれもステキすぎる!あなたはどこまで知っていますか?

任天堂とDeNAが業務・資本提携を発表して業界が賑わってますが、その影にひっそりと発表された任天堂の新たな新ゲーム機プラットフォーム「NX」
この「NX」というのは正式名称ではなく、コードネームということなので正式に発表されるときにはまた名前が変わるでしょう。
NXってまた結構適当だなと思いましたが、過去のゲームハードはどんなコードネームだったっけ、と気になったのでちょっと調べてみました。
任天堂

まずは任天堂から。
さすがは玩具メーカー。コードネームにも遊び心を垣間見ることができます。
Home Video Computer
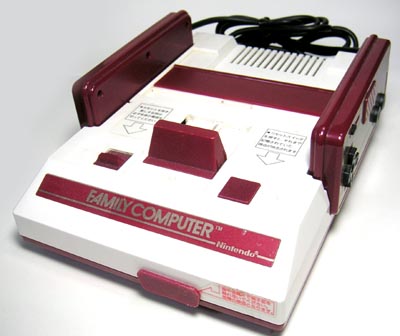
ファミリーコンピューターのコードネーム。
けっこう無骨な感じですね。家庭用ビデオゲームコンピューターみたいな意味合いでしょうか。
正式名称の方がキャッチーで良いですね。
ちなみにスーファミは「Super Home Video Computer」
Dot Matrix Game
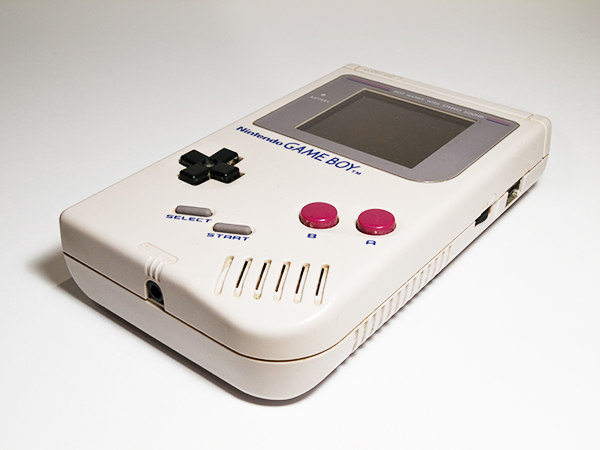
GAMEBOYのコードネーム。
これはおそらく、ゲームボーイの画面が「STN反射式モノクロ液晶のドットマトリクス式」を採用していることから由来してます。
ドットマトリクスゲーム。かっこいい。
Project Reality

NINTENDO64、通称ロクヨンのコードネーム。
リアリティ追求しよーぜ的な意気込みを感じます(適当)
ちなみにロクヨンは、企画発表当時、山内溥さんによって「ウルトラ64」として発表され、海外では正式名称の前にこちらの名称が広まったみたいです。
ウルトラ64。古くさ渋くて良い。
Atlantis
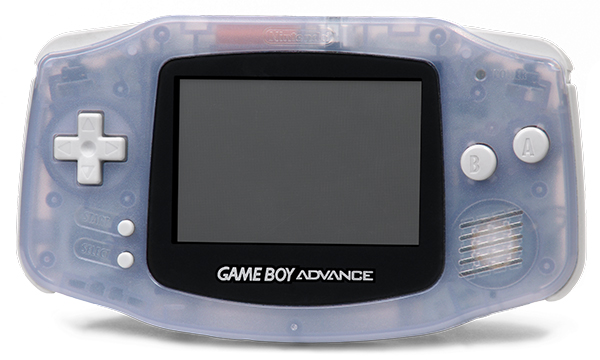
ゲームボーイアドバンスのコードネーム。
アトランティスというのは、哲学者プラトンによる著書「ティマイオス」に登場する「王国島」のこと。強大な軍事力を背景に世界の覇権を握ろうとしたものの、ゼウスの怒りに触れて海中に沈められたとされてます。
なかなか中二臭いけとちょっと縁起悪くないですか任天堂さん。
Dolphin

ニンテンドーゲームキューブのコードネーム。
ドルフィンとはもちろん「イルカ」のこと。
イルカは、体重に対する脳の割合が人間に次いで多いことで有名で、その知性の潜在性は古くから指摘されてます。
「こうみえて、性能いいんだよ?」ってことなんでしょうかね。
Nitro

ニンテンドーDSのコードネーム。
ニトロというのは、ニトロ化合物の事でしょう。
ニトロは爆発性を持つので、自動車等のエンジンの出力を一時的に上げるシステムの俗称にも使われてます。映画ワイルド・スピードでよく使われるシステムですね。「加速すっぞ!」とかそういうことなんですかね。
実際、DSで加速しましたね任天堂。
Revolution

Wiiのコードネーム。
「革命」とは、権力体制や組織構造の抜本的な社会変革あるいは技術革新などが、比較的に短期間に行われること。
また大きく出ましたね任天堂さん。とはいえ、Wiiによってゲーム人口の大幅な拡大に成功しているので、あながち革命を起こしたと言っても過言ではないかも。
Project Cafe

WiiUのコードネーム。
カフェ…急におしゃれな感じになりました。
「人々が集まる、憩いの場」みたいなイメージですかね。カフェ。
Sony Computer Entertainment
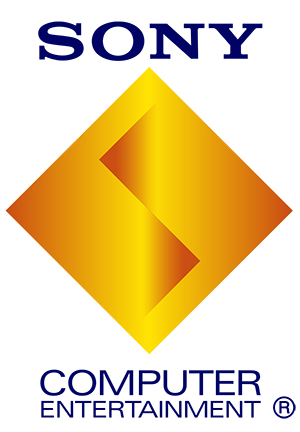
続いてはソニーのゲームハードたち。
任天堂にくらべると、ちょっと洒落っけがあります。
PS-X

PlayStationのコードネーム。
ひねりが無いというよりは、開発段階からPlayStationという単語は確定していたという事でしょう。
元々、仕事で使うコンピュータを「ワークステーション」と呼ぶことに対して、遊びで使うコンピュータという意味で「プレイステーション」という名前に決定されたと言われています。
PS1,PS2,PS3,PS4,PSP,PSV,PSM,PSN…キリがないですが、任天堂がハードの名前を変えていくのに対して、ソニーはPSの名を命名し続けているところにロマンを感じます。
Next Generation Portable

PlayStation Vitaのコードネーム。
発表当時、PSPがメチャクチャ売れていたので、そのまま「次の世代の携帯ゲーム機」ということをコードネームから宣伝していくという、まさにソニーっぽいコードネームですね。
略してNGP。ネオジオポケット発売キター!とかいって騒いでた人たちもいましたね。
Arc

PlayStation Moveのコードネームです。皆さん、覚えてますかこのデバイス。
アークというのは「弧」とか「弓」という意味。
まぁなんとなく意味はわかります。
Orbis

PlayStation4のコードネーム。
オルビス(オービス)というのはラテン語で、「世界、国、地域、円、輪、繰り返し」などの意味があるそうです。
かっこいいですね。意味的にもプレイステーションの進化版みたいな感じがしますし、PlayStaion4じゃなかったらOrbisでも良かったな。
マイクロソフト

海外の企業であるマイクロソフト。
コードネームにもどことなく海外感を感じます(適当)
DirectX-box

Xboxのコードネーム。
プレイステーションと同じく、コードネームがすでに製品名に近いパターンですね。
「APIにDirectXが使われている箱」「未知の箱」みたいなところが由来なんじゃないでしょうか。
Xenon

Xbox360のコードネーム。
Xenonというのは、Xbox360のCPUに使用されている、マイクロプロセッサの名前。
Xboxといい、マイクロソフトは中身の名前を本体につける事が多いんですかね。
Project Natal

キネクトのコードネーム。
ナタルという言葉には、「出生(出産,分娩)の」という意味があります。
「新しいハードの誕生、そして、生まれたままの姿で遊ぶゲーム機」みたいな意味でしょうか。
プロジェクトナタル。響きが外人っぽい。
Durango

Xbox ONEのコードネーム。
Durango(デュランゴ)という言葉自体に意味はなく、メキシコの地名みたいですね。
その他だと、レーシングチームの名前だったり、車の名前だったり…。
なぜこのようなコードネームが付けられたのかは謎です。
SEGA

最後はセガ。
セガは一貫して惑星の名前を付けるのが恒例だったみたいですよ。
Mercury

ゲームギアのコードネーム。
マーキュリーは水星ですね。水銀、という意味もあるみたい。
それ以外だと、有人宇宙飛行計画の「マーキュリー号」とか有名でしょうか。
あとは…あとは…特にないな。
Mark V

メガドライブ(GENESIS)のコードネーム。
セガマーク3(SG-1000III)、マスターシステム(SG-1000IV)の次という意味で、マーク5になったのでしょう。
Jupiter
実際には発売されていない幻のゲーム機のコードネーム。
メガドライブの次世代機(セガサターンに当たる)がこれに当たると噂され、当時は詳細はスペック等も報道されましたが、実際には発売されず。
当時、ゲーム機事業を統括していた岡村秀樹さんは、Jupiterの存在を否定していたそうです。
言いたかった…「ジュピターなのにサターンなのかよ!」って。
Saturn
Venus

1995年に発売された、ノーマッドという海外市場向けの携帯ゲーム機のコードネーム。
「ノマド」という単語は今でこそ流行ってますが、今から20年前に携帯ゲーム機にその名をつけちゃうセガ。やっぱり早過ぎる。
Mars

↑画像はメガドライブに乗っかった状態
スーパー32Xという、メガドライブ用の周辺機器のコードネーム。
これは、セガサターンががCDROM機気なることが決定した結果、発売が見送られたカートリッジベースの次世代機を、そのままメガドライブの周辺機器にしてしまえという画期的なデバイス。
どういうこっちゃねん。やばいなセガ。
Neptune
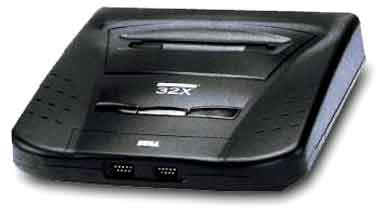
上記のスーパー32Xとメガドライブの一体型ハード。
セガサターンの発売が迫っていて、バッティングしそうだということで発売こそされませんでしたが、そんなもん発売しようとしてたんかい!って印象。
いいねセガいいよ。
KATANA

Dreamcastのコードネーム。
おっと急に切り口変えてきましたね。刀だけに。
片方にしか刃が無い武器、カタナ(片刃)、セガはドリームキャストにどのような思いをのせていたんでしょうか。いっちょ切り込んでいくぞ!みたいな感じでしょうか。
わかんねーや。
以外とちゃんと名付けられていた
任天堂の最新プラットフォーム「NX」はおそらく「任天堂のX(未知)」みたいな意味なのでしょうが、比較的その他のゲーム機のコードネームもなんらかの意味を持って付けられていることが多いですね。
それこそ、対外的な印象や、広告展開上の問題を無視した、純粋に開発者が我が子に名付けるようにつけられるものですから、必然的にそのハードを言い得たものになるということでしょう。
ちなみに、ぼくの個人的なお気に入りは、Orbisです。
みなさんはどれが好きですか?